この記事は2019年以前他サイトに執筆したものを引越し掲載しています。
転職してWebデザインをやってみたいけど、職業訓練校ってどのくらいの時間で具体的に何をやるんだろう、という人向けに記事を書いてみます。
私は半年間の職業訓練を経てWebデザイナーとして就職しました。これを書いている今からさかのぼること4か月前に卒業したので、まだ記憶が新鮮なうちに情報を残しておこうと思います。
そもそも何を習う?(知ってる人は飛ばしてください)
Webデザインで学ぶべき範囲はとても広いです。でも基礎は意外とシンプルで、とりあえずこれを知っていればWebページは作れます、という部分だけを学校で学びます。

まず、大別すると以下の2つを学びます。
- デザインツールの使い方
- Web言語の書き方
デザインツールの使い方
まずデザインソフトの使い方です。主にAdobeという会社の「illustrator(イラストレーター)」と「Photoshop(フォトショップ)」です。
デザインの現場では圧倒的な割合でこの2つが使われているからです。事務で言うとMicrosoft社のWordとExcelみたいなものです。
- 「illustrator(イラストレーター)」…主にイラストを描く。
- 「Photoshop(フォトショップ)」…主に画像(写真)の編集。
この2つについて主に操作方法を勉強します。



でも美大ではないので、デザインのコツみたいな内容はほとんど学べません。
あくまで「操作の仕方」を勉強します。パソコン教室でWordを勉強しても文章が上手くはならないのと同じ感じです。
Web言語の書き方 HTMLとCSS
次にWeb言語の書き方ですが、これは主にHTMLとCSSというのをやります。今このページを表示しているときにも活躍してくれているWeb用の言語です。
- 「HTML」…ページの骨組みを作る言語。家を建てることで言うと基礎や骨組み。
- 「CSS」…HTMLで組んだものに飾り付けをする言語。壁の色を決めたりするイメージ。
その他の学習 動きを出すなど
あとは他のことも少しだけ学びます。私が受けたカリキュラムでは「jQuery」というものを学びました。これで「動き」を出します。
Webページを見ているといろんな動く仕掛けがあります。スライドが流れていたり、押すとページの一番上にスルスルと戻ったり。そういうのを作れます。家づくりの例で言うと、ボタンを押したら電気がつくようにする、みたいなイメージです。



ではこれらが半年間でどうやってスケジュールされていたかです。
半年間のカリキュラム
半年間のざっくりとした内訳です。
デザインソフトの使い方を2か月、Web言語を3か月、最後に卒業制作が1か月でした。



初日にPCのセキュリティや安全衛生(姿勢や目の疲れとかの話)の授業があり、2日目から早速授業に入ります。
| ケ月目 | ソフトウェア・言語 | 内容 | 課題制作 |
| 1 | illustrator(イラストレーター) | グラフィックデザイン・イラスト | 〇 |
| 2 | Photoshop(フォトショップ) | 画像編集・写真加工 | 〇 |
| 3 | HTML・CSS | WEBページの基礎 | 〇 |
| 4 | HTML・CSS(レスポンシブ) | 上に加えてスマホ対応させます。 | |
| 5 | jQuery | さらに動きを出していきます。 | |
| 6 | 卒業制作 | 集大成のWEBサイトを作ります。 | 〇 |
※表一番右の課題制作というのは各学習の区切りに行なう各自の作品作りです。これについては後述します。
なお、こういうカリキュラムは訓練校ごとに公開されているはずなので、申し込み前に把握してできる範囲でイメージしておくといいと思います。
授業日数・内容
デザインソフト(illustrator,Photoshop)の使い方
学習日数
| 日数 | illustrator(イラストレーター) | Photoshop(フォトショップ) |
| 14日間 | テキストを進め、区切りで小課題 | テキストを進め、区切りで小課題 |
| 3日間 | 課題制作 | 課題制作 |
| 1日間 | 課題発表 | 課題発表 |
私のところは上記のカリキュラムでした。実際には授業や課題制作の進み具合で日数の変動はありましたが。
それぞれのソフトについて18日間、約1か月弱で基本操作を学習します。以下もう少し詳細を。
illustrator(イラストレーター)の学習内容
先にも書きましたが、やるのは操作の仕方です。なので、授業を受けてもカッコいいデザインが作れるようにはなれません。
これらのソフトはかなりベテランでもすべての機能は使いこなせないかもしれないほど多機能です。当然授業でやる部分は基礎の基礎に絞られます。
まず最初の数日で、超基本の図形を描くとか変形するとかをやります。かなりゆっくり進んだのでパソコン初心者でも大丈夫な感じでした。
| テーマ | 内容 | 難易度 |
| 基本オブジェクトの描画 | 丸とかの図形を描く、並べる、変形する等 | 低 |
| 描画ツールの使い方 | 主にペンツールという自由に描けるツールを使う | 高 |
| 色のコントロール | グラデーションや透過といった機能を使う | 中 |
| 応用的な加工 | 立体、写真の利用など | 中 |
| テキストと画像のコントロール | パンフレットやロゴなどに使用できる加工・調整法 | 中 |
イラストレーターは基本的に自由に直感操作できるので、誰もが楽しめると思います。



Windowsのペイントとかを使って遊んだことがある人ならそれが超高機能になったイメージです。
難易度は個人的な主観です。2番目、高にしたのは「ペンツール」という曲線などをきれいに引くためのツールが多少練習が必要だからです。※以下難易度を高としているものが登場しますが、学習範囲の中では相対的に難しいほう、というだけです。Webデザインの学習内容は全体的にやさしめと思います。
フォトショップの学習内容
イラストレーターよりちょっとだけとっつきにくくなります。いきなり写真加工とかではなくて、最初に基礎の基礎となるフォトショップの概念を学びます。
| テーマ | 内容 | 難易度 |
| 加工の前段階となる基礎 | 選択範囲、マスクといった加工の前段階の操作 | 中 |
| 写真の補正 | 写真のごみや歪みを取り除く、色合いの調整 | 中 |
| 写真の加工 | 動感を加える、照明効果を与える等 | 高 |
| 写真の合成 | 写真をつなげて一枚に見せる、背景を変える等 | 中 |
| イラストと文字 | (Photoshopももちろんイラスト・文字を扱えます) | 中 |
最初に学習する「マスク」などの基礎操作、また「レイヤー」という概念を理解することが大切です。これを習得することで「どの部分に」あるいは「どの写真に」操作するのかを指定することができるようになります。ここが意外と慣れないと混乱しやすいのですが、逆にこれさえできるようになれば大丈夫です。



illustratorとPhotoshopの授業の進み方は以下のようにシンプルでした。
- 先生がテキスト通りに操作を実行して見本を見せる
- 「では各自やってみましょう!」(全部テキストにやり方が書いてあるのでそれを見ながらでOK)
- 必要に応じて先生のフォロー
- これを繰り返した後、今度はやり方が書いてない(テキスト以外の)小課題で練習
上の流れで進んでいました。はじめての人でもぜんぜん大丈夫ですが、逆に言うとちょっと経験があるという人は訓練校では物足りないと思います。
Webページ制作(HTML・CSS・jQuery)



ここから本格的なWebページ制作に入ります。
| テーマ | 内容 | 難易度 |
| HTMLとCSS基礎 | HTMLとCSSの基礎、PC表示の簡単なページ作成 | 中 |
| レスポンシブ対応 | スマホなどのデバイスでも最適表示する技術 | 高 |
| jQuery | スライドやタブの開閉などの動きをつける技術 | 高 |
HTMLとCSSは広い意味ではプログラミングですが、勉強は得意じゃなかった、あるいは文系だという人でもたいてい問題ないです。必要なのは慣れだけです。
後半デバイス幅に対応させたり動きをつけたりする部分は難しく感じる人もいるかもしれません。でも動きはプラグインなどを使って組み立てることもできるのでそんなに心配ありません。プラグインというのは、料理で言うと「○○の素」みたいな感じです。基本の焼く、煮る(HTMLとCSSでの組み立て)がしっかりできていれば、ササッと加えて出来上がり!というわけです。実際制作現場では時間の関係もあり、自分で組める人でもプラグインを使うことが多いです。



こちらも授業の進み方は基本テキスト通りです。
- 各セクションの概要を先生が説明するので、テキストを見ながら聴く。
- その後、実際に手を動かしてコードを書き、ブラウザに表示をさせてみる。(テキストのサンプル通りに書く)
- これを繰り返していろいろな技が蓄積されてきたら、学んだことを応用して1枚のページをつくる。
基本的にはテキストに沿って進むので、難しそうだなと思っても大丈夫です。よくわからなくてもテキストを写す作業を繰り返していくとどんどん慣れていきます。
課題制作・発表
それぞれの学習内容の区切りでは、学んだことをもとに各自で制作を行ないます。



ここでの制作も就職活動用の作品集に含められるので大切です。
下の表にあるように私の受けた訓練では全部で4回課題制作と発表がありました。
| 内容 | 制作期間 | 課題のテーマ |
| illustrator(イラストレーター) | 3日 | ポスター制作 |
| Photoshop(フォトショップ) | 3日 | バナー数種類(5~6個) |
| Webデザイン(レスポンシブではない) | 7日 | 2ページ以上のWebサイト |
| Webデザイン(卒業制作・レスポンシブ) | 17日 | 自由(できれば実在店舗など) |
上記表は本来のカリキュラム日数でまとめています。実際には、Photoshopで生徒のリクエストにより制作期間延長→代わりに卒業制作期間は3日ほど短縮、など変更がありました。
課題ができたら簡単な発表をやります。就職訓練の一環として、本当はプレゼンのような形でやるという前提でした。



が、実際はゆる~い雰囲気の発表会みたいな感じでした。
一応みんなの前に出て作品の説明とかをするので気恥ずかしかったです(めちゃくちゃ下手くそだったので)。
私は最初の課題で上手い人のをみて軽く心を折られました。と同時にみんなからアドバイスをもらえたり刺激をもらえたりするので貴重な機会でした。
卒業制作
最後の一か月弱で、今までに学習したことを用いてWebページを制作します。数ページの小規模なホームページです。スマホ対応はもちろん、スライドなど動きをつけていきます。
実在の店舗をモデルに作らせてもらうと楽しいですし、とても勉強になります。私もクライアントワーク(訓練校の近くの居酒屋さんのHPを作らせてもらいました。)をやりました。
その他就職関連でやること
ハロワに来所(毎月1回)
月1回指定日にハローワークにいきます。失業保険を受給したことがある人はご存知だと思いますが、この日にサボると大変というやつです。また卒業後も就職が決まらない人は最大3か月まで月1回の来所が必要でした。
キャリアコンサルティング(全3回)
略して「キャリコン」。担当講師ではなく、訓練校の責任者や担当の人と20分ほど進路相談などをします。
私の場合、初回は授業についていけているか、馴染めているか、今までの仕事は?、などが話のテーマでした。後半は就職関連のことを具体的に相談したりしました。
就職案内・講話(全4回)
職業人講話という形で4社から話を聴く授業がありました(2時間×3社+5時間×1社)。
内容は自社事業の紹介であったり、Web業界に関わる知識などでした。講義の質はさまざまでした。講義の最後には登録などの用紙が配られるので就職機会の一つになり得ます。もっとも周りにはこういった形で就職した人はいませんでしたが。
実務研修(あるところもある)
訓練校によっては、企業で実務を体験できる研修があります。私の通っていた訓練校では実務研修はありませんでした。



いいな~実務研修。就職した今でも受けてみたかったなあと思っています。
自身の体験は書けないので、同じ会社の訓練卒の先輩に聞いたことを書いておきます。現場でやらせてもらった内容は、既存サイトの細かい修正とかだったそうです。
自分では指示通りできたつもりで報告しても、ここの幅が少し違うとか細かいところを指摘されることが多かったそうです。その時は聞いても納得できないくらい細かいことも多かったとか。ちなみに制作会社の実務は、社内のやり取りもクライアントからの要望もそういった細かい修正など多いです。
こういった学校の制作ではやらないところを在学中に経験できるのは大きいと思います。学校は基本的には好きなように作るだけですから。
また私が就職活動中に感じていた不安と手探り感は、現場を全く知らないことからくるものでした。一度でも、雰囲気だけでも、現場を知れるのは大きいと思います。



以上のことから実務研修がある訓練は積極的に検討してみる価値があると思います。
ポートフォリオ制作(主に訓練期間の後半、自主的に)
ポートフォリオというのは作品集のことです。紙とWebの2パターンあります。Webデザイナーの就職活動には必須と言われています。
なくても応募できるところもありますが、未経験でこれもないとなるとまず選考対象にすらならないと思います。逆にポートフォリオが素晴らしければ未経験でも十分選考してくれるところも多いです。



それなりのものを作るのは結構大変です。時間がかかります。
ですが訓練のカリキュラム上はそのための時間は特に振り分けられていません。ですので作らない人もいますし、Webデザイナーへの就職意思がある人が自主的に作っていた感じです。
半年後には就職しているのが目標ですから、カリキュラムの後半はこれを作りながらということになります。就活もどんどん行なう人はけっこう忙しくなるはずです。もっとも意識が高い人ほどポートフォリオに載せることを前提に授業の課題作品などをストックしていました。私の場合訓練期間中はWebのポートフォリオを作るのが精一杯で、紙のポートフォリオは卒業後に少しずつブラッシュアップしていきました。
訓練校は、とりあえずやってみたい!という人にはおすすめ
職業訓練校のカリキュラムと授業内容、いかがでしたでしょうか。Webデザインやってみたい!と思っている人は無料ですので、積極的に検討してみるとよいと思います。
人生かけてて超本気!とか、ちょっとは経験あるんだけど、という人には正直おすすめしません。物足りないとかもっと高いレベルを、と感じてしまう可能性が高いです(実際クラスメートに何人かいた)。そういう人は専門学校や民間のスクールも調べてよく検討することをおすすめします。
実はまだまだ書きたいこともありますが、長くなってしまったのでこの辺でこの記事はおしまいにします。興味がある方は他の記事でも職業訓練について書いているので参考にしてください。
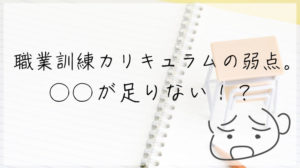
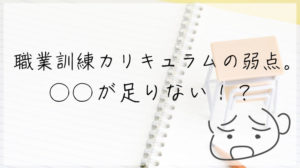
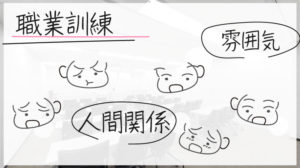
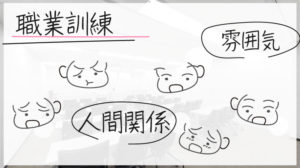
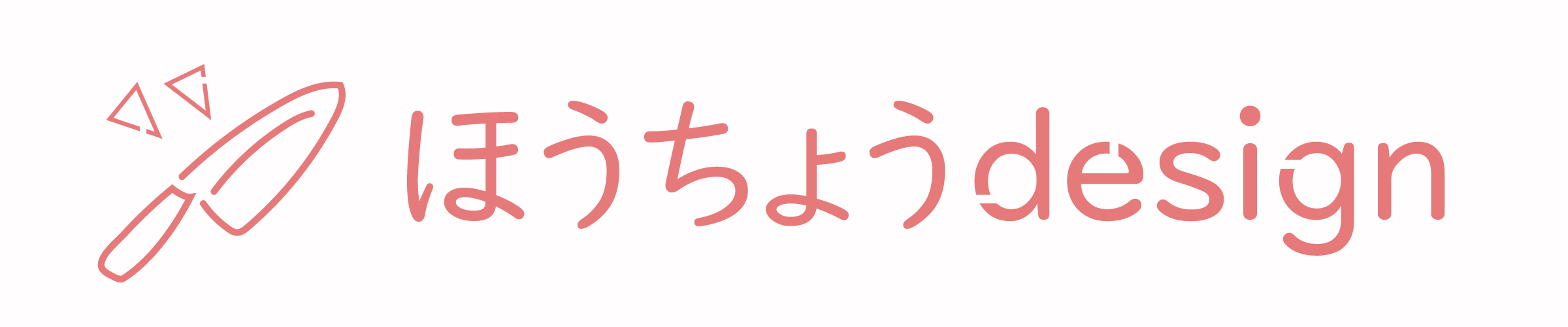
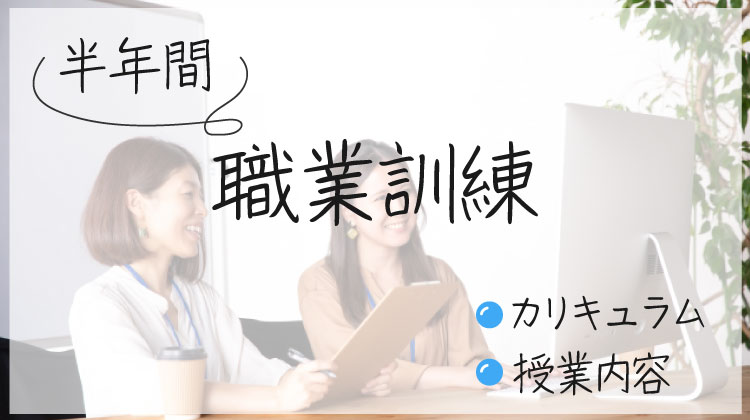
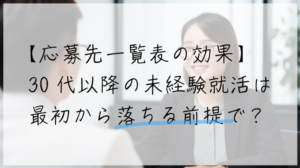
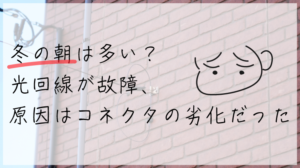
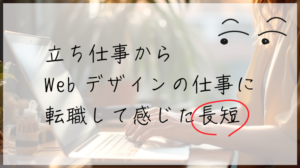
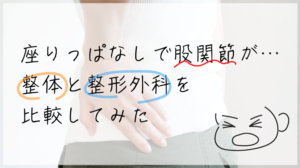
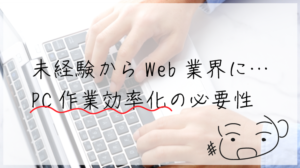
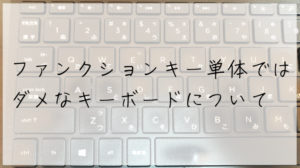
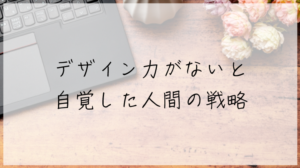
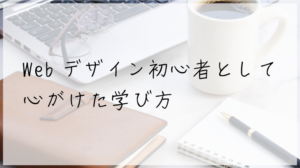
コメント