この記事は2019年以前他サイトに執筆したものを引越し掲載しています。
未経験Webデザイナーを目指す上でのポートフォリオ。最初はそれなりの作品数を作るのも大変です。

当初載せられる作品数も少なかったので、とにかく数を増やすことに苦労しました。
ただ数だけでは書類選考も通過できず、これではだめだと思っていろいろブラッシュアップしました。
この記事ではポートフォリオで差をつけるために、35歳未経験だった私が行った方法を書いてみます。見せ方のテクニックなどではなく、内容という部分に焦点を当てています。
差をつける=個性を出す、は×
未経験者だとオリジナリティを出すという意味での差別化を考えたくなってしまいがちです。私がそうでした笑
でも、この方法はよほどセンスがよくないと難しい気がします。また見せ方で目をひいても、最後は客観的・実務的な力が問われると思います。
ポートフォリオは自己表現のツールというより、基本的にはこれまでの実績をアピールするための作品集。本来はプロとしての実績。
でも未経験者の場合、その肝心の実績がないです。
でも採用側は仕事としての実力が知りたい、「いいかもな」と思った人でもその裏付けがほしいです。
ではどうするか。私はセミプロとしての実績を作る、という作戦をとりました。
具体的には
- 実在の企業・店舗のサイトを作る
- クラウドソーシングで応募する・受注する
学校の課題だけではなく実際の世の中と関わっていくということです。



学校の課題よりもクライアントワーク。後者の方が比重として多くなるくらいが理想と思います。
シンプルですが本気の人以外はあまりやっていないので他の未経験者と差をつけられます。学校で作った課題を載せてるだけの人も多いからです。
ただいずれの場合も権利関係は十分に確かめ慎重にする必要があります。特に提供された写真素材や企業ロゴなどです。すべてクライアント側にも掲載許可をもらうこと。
実在の企業・店舗のサイトを作る
実務に一番近いのは、実在するクライアントを相手に制作するということです。特に制作会社に応募するならこれは最も評価されると思います。
知人友人の会社、いきつけのお店などを当たってみることができます。
意外とホームページを持っていない、あるいはリニューアルを考えているところは少なくありません。発注すると高いし、WIXなどを使うとしても自分で作るのは忙しくてできない、という人は多いです。
理想を言えば、お金をもらって公開・運用する、というところまでいければ最高です。でもさすがにそれは双方負担が多いですから段階を踏みます。
公開・運用を前提に制作してみる、という方法です。



前提と言ってもあくまで「将来的に活用を視野に入れて」というニュアンスでOK。
「まず作らせてください。もし完成品が気に入って運用の準備ができたら使ってください。その場合サーバーの契約やドメインの取得、メンテナンス等については、お金や契約上のこともあるので受けるのは難しいかもしれません。(もちろんやり方など協力はします)」
という形をとることもできます。私が実際にやった方法です。
これならお互いハードルが低く、こちらも負担がない形で話が進められます。



そしてこの方法の一番のメリットは、面接時に例えば以下のように言えることです。
「このサイト作品は実際に公開・運用を前提に作りました。今、クライアントに検討してもらっています。」
もちろん知人等のお店をモデルに運用前提でないサイトを作ってもいいと思います。それだけでも架空のお店のものをつくるよりはだいぶ評価が高いと思います。
私の場合訓練校の卒業制作が自由課題だったので、居酒屋さんのサイトを制作しました。訓練校の近くの小さな個人経営のお店で、お昼など何度か食べに行きましたがHPは持っていませんでした。そこで話をしてみると、意外にも喜んで応じてくれました。少人数で回しているお店だったので取材の時間を取ってもらうのがちょっと大変でしたが。
制作したHPを本当に使ってもらえそうな場合
もしかしたら練習で作らせてもらったサイトを本当に使いたいと言ってもらえることもあるかと思います。作品を気に入ってもらえたということですから、うれしいですしきっと自信になります。
でもその場合でも先述のように運用や保守は引き受けないようにした方がいいと思います。
サーバーなどの問題もありますし、未経験者が商用のサイトを管理するのは大変すぎます。またHPが原因でクライアントとその顧客との間でトラブルが起きた場合等リスクもあります。
あくまで担当するのはデザイン制作(サーバー等も初期設定まで)という形で最初から話を進めておき、就活とスキルアップにエネルギーを注ぐ方がよいと思います。
クラウドソーシングで応募・受注
「ランサーズ」や「CrowdWorks(クラウドワークス)」などクラウドソーシングの作品を載せているとその活動が評価されます。とはいえ未経験だと受注はハードルが高いです。
そこでコンペという方法もあります。採用されればお金が発生しますから、そうなれば単発とはいえ立派なお金をいただく仕事です。



私も合格した会社では、面接時にこの点注目してもらえました。
私の場合コンペで採用されるまで毎日一作品は応募する、という目標で続けていました。
主にチラシやバナーでしたので、慣れてくると1時間などで作れるようになりました。最初はバナー1個に3時間などすごい時間かかってましたが。
ポートフォリオや面接のためだけではなく、本当に自信と力がつくので就活生にはおすすめです。ただ就活ポートフォリオのためにクラウドソーシングを利用するという姿勢に傾きすぎないことは大切と思います。クラウドソーシングはビジネス、契約の場です。ネット上では発注者の顔は見えませんが、しっかり相手がいるという点を忘れないようにする必要があります。
また作品数を増やすために利用、みたいな姿勢だと結局面接でも見抜かれて評価されないと思います。やるからには本気でクラウドソーシングの仕事をするという心構えが必要です。
なおポートフォリオ掲載の可能性という点から考えると、制作会社からの二次請けみたいなものは避けたほうがよいと思います。私の場合個人経営のお店など直のやつばかりだったのですんなり掲載許可もらえました。
採用されなかった作品について…コンペは採用されないことがほとんどです。これらの掲載許可をもらうのは基本的に難しいと思います。提供素材などが多い場合は特に。少なくとも発注者側に手間を取らせてしまいます。
WebポートフォリオはWordPressでつくる
ポートフォリオは紙とWeb両方作っている方が多いと思います。



が、やはり「Web」デザイナーですからWebの方が重視されていると、面接を通じて感じました。
WebのポートフォリオはWordPressで作ったのですが、これが意外にも評価されることが多かったです。
既存テーマとプラグインを使って構成しただけ(つまり一切コードは書いていない)ですが、それを説明してもWordPressの使用経験として評価されました。
つまりWordpress案件が多い制作会社の場合、管理画面等に慣れているかということ自体も考慮するようです。ちなみにWordPressにはポートフォリオに適したテーマやプラグインもあります。
その応募先企業に向けた作品
企業はどの応募先にも同じポートフォリオを持っていっているんだろうな、と思ったら何も感じてくれません。業界に合わせて順番や見せ方を変え、作品数に余裕があればチョイスを変える等の工夫があるとよいです。
そしてある意味最高の作品は、その企業や業界に入りたいから作ったというものです。
事業会社ならそのHPをコピーしてコーディング、あるいは商品のバナーやLPを制作する、など。あるいはターゲットを絞っている制作会社ならその業界に関するページを作るのもいいかもしれません。
媚びたり点数稼ぎで作ったのではもちろんダメだと思います。むしろ本当にその会社で制作の仕事をしたいと思ったら、その会社や事業、業界に関わるものを作ってみたいと思うのは当たり前、という意味合いです。
私がこれをやろうと思ったのは、ある業界だけを専門にしている制作会社に応募した時です。一次面接で話をして、ここで働きたいと思いました。なのでその会社が制作しているものを自分が今どれだけ作れるか家でやってみよう、と単純に思いました。家に帰るなり制作実績から選んだものをコピーしてコーディングしはじめました。



二次面接の前に今の会社に内定したので、成果をみせる機会はありませんでしたが…。
さすがに全部の応募先にやってたら時間が足りませんので、このように本当に入りたいと思った企業、最終面接に進めそうで最後の決め手を出したいときにやってみるのは手かもしれません。
またこうして作ってみた作品はその企業に落ちても無駄にはなりません。少なくともトレーニングにはなります。
「ポートフォリオのため」を超えること
さて、ここまでポートフォリオで差をつけるという内容でした。
もう一度まとめると
- 実在の店舗・会社をモデルにHP等を作らせてもらう
- クラウドソーシングで制作する
- 応募先企業に特化した作品を制作する



加えるとWordPressで作ると評価されることが多め(特に制作会社)。
まとめて書くとさらっとしていますが実際これを全部やるとなかなかにたいへんです。
でもやったらやった分だけ必ず自分に返ってきます。実際今制作の仕事をしていて、就活期間中の活動はそれなりに生きているなあ、と感じています。
ポートフォリオの作品作りって、実はやればやるほど楽しくなります。最初は、学校の架空の課題よりも難しく一つ作るのが大変…と感じますが、だんだん苦じゃなくなってきます。
私もポートフォリオに載せられる作品が足りない!という頃は辛かったです。でも最後の方は、載せきれないからどれをチョイスしよう?となっていて、この頃にはもうポートフォリオのために作るというより単純に楽しいからクラウドソーシングで作ってました、笑。



楽しみながらポートフォリオが充実させられるくらいになれば自然と内定は近づいているはずです。
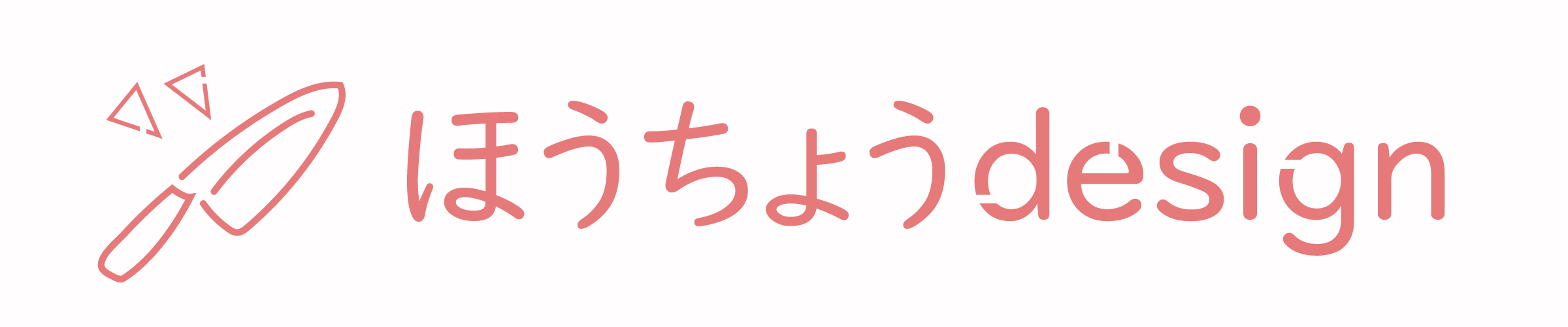
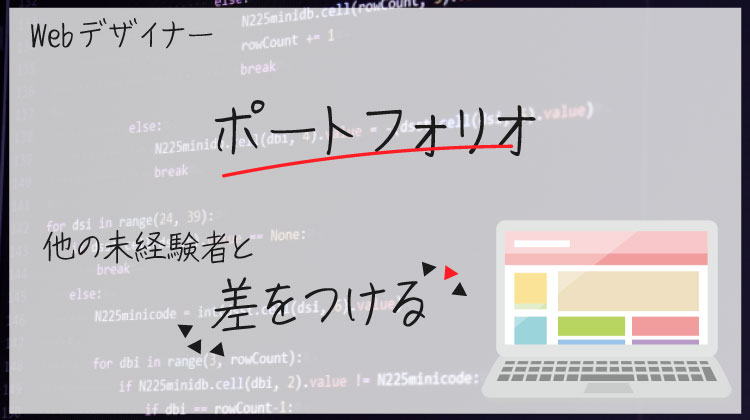
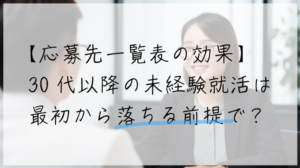
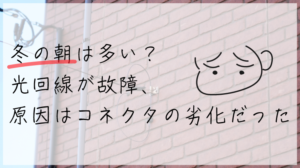
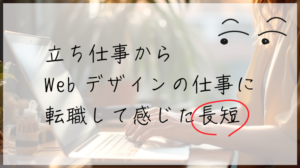
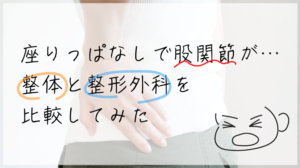
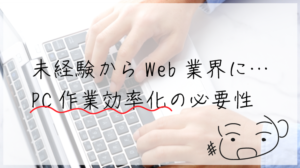
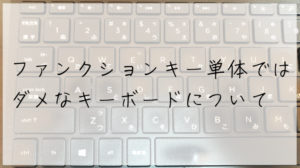
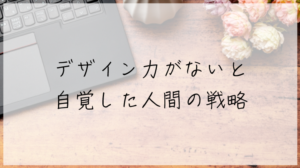
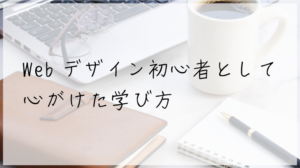
コメント