この記事は2019年以前他サイトに執筆したものを引越し掲載しています。

私はHSPというタイプらしいです。
言葉自体最近知ったのですが。「23個中12個以上当てはまるとHSP」というリストでほぼ全部当てはまりました。HSPは簡単に言うと敏感で感受性が強い人です。
他にも幼少期吃音や子どもの頃集団生活を嫌がる、環境の変化に対して身体が弱いなど典型的なHSP(HSC…そういう子ども)の特徴だらけ。
あまりにも自分が当てはまるので、提唱者(エレイン・N・アーロン)の本を2冊読んだのでその感想記事です。
HSPの定義などについてはHSPにとってWebデザイナーという職業はたぶん向いているの記事で書いてます。
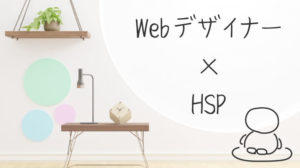
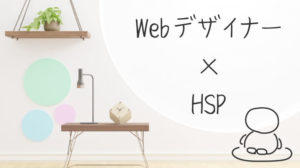
良くも悪くもクセのあるタイプの本
2冊読んだ結論から言うと、正直HSPという説を信頼はできなくなりました。



たいていの物事はネットなどで概念を知った時点より、書籍や原典に触れたときのほうが信頼が深まるのですがその逆でした。
あ、決して否定しているのではなく曖昧にしておきたくなった感じです…ちょっと根拠が薄弱に感じるというか。
と同時に、はっきりタイプとして定義・分類しなくとも、こういう視点を親や先生が頭の片隅に入れておくのはとても大切なのではないかとも思いました。
以下否定的、肯定的それぞれ私の感想。
※原語で読んだらまた違う印象になるのかもしれません。翻訳者のクセなどはわかりませんので。
まず否定的・批判的な感想から
総じてHSPという概念がHSPとされる人には強烈に支持されるのに、一般的には(少なくとも日本では)あまり浸透しないことに納得してしまいました。
とにかく著者(提唱者の博士)がHSPに対してやさしすぎるのです。特にHSPは優秀で特別だって感じが出すぎています。
自己を必要以上に否定してきた人を助けたいと思っているのでしょうからその目的を達成する上ではいいとは思います。ただこういう書き方だとHSPが非HSPから客観的に公平に理解されにくいと思いました。
さらに極端に言うとHSPの自己肯定感の低さに取り入ろうとしている感じさえ受けます。もちろん著者の動機は悪くなくて、HSPを助けたい・肯定したいという良いものなんでしょうが、バランスを欠いているので結果的にそう受け取ることもできてしまう、という意味です。
また学説として提唱したいのか、HSPの人を対象にした自己啓発的なものなのか。主に後者だと思いますが、終始その両方がごちゃごちゃ展開されている感じを受けるのでそこが残念でした。ごちゃごちゃ書くことで根拠の薄弱さをうやむやにするテクニック?とかさらに勘ぐってしまう…。
内容的に特に気になってしまったのが、本の中に著者自身の「勘」「第六感」みたいな表現が出てくること。HSPは「わかってしまう」らしいので、HSPである著者も「私にはわかってしまうのだ」という寸法で話が展開する部分があって驚きました。なんだろうその根拠、笑。読者がHSPだけならまだいいですが、非HSPが読んだら懐疑的になるだけ…。
もちろん取材・研究はされていますが、こういった疑わしく感じさせる部分の方が強くなっていると感じました。
こうなってくると(穿った見方すぎるかもしれないですが)、HSPの割合が5~6人に1人というのも絶妙にコントロールしている感を受けてしまいます。これ以上多いと希少価値がなくなるし、少ないと支持者が減ってしまう。だからそうなるように境界線を設置したように感じてしまいます。
あとは繊細さや感受性って、その強弱よりも方向性の方がバラバラに分かれる気がします。例えばWikipediaで「恐怖症の一覧」を見るとあらゆる「恐怖症」があって、どれにも当てはまらない人などいないかのような多様性を感じます。
それを高低・強弱っていう二次元で定義づけするのは困難。だから本の中でも、特定の特徴についてぜんぜん当てはまらない子(人)もいる、というのが多発してしまっています。結果的に外れない占いみたいになっているところも。
わかりやすい切り口・説として世間に浸透させるとしたら、このまとめ方がギリギリのところなのかな…う~ん。
それと子育てという面では、「ひといちばい敏感な子」はただの甘やかしにつながりかねないなあという感じも受けました。HSC(Cはchild)をひいきしてしまっている感が強すぎて。
全体を通じて「公平性を重視」するという定義のHSPの著者が、HSPを必要以上に持ち上げている感がやや残念でした。
肯定的な感想
ちょっと疑念というか否定的な意見が強くなってしまいましたが、ここから読んでよかった点です。
総じて、こういう目立たないタイプの人たちがいる、決して劣っているわけではない、むしろ長所もたくさん持っているってことを明確に発信してくれたのはとても意義があると感じました。
さんざん否定的なこと書いておいてなんですが、著者は素晴らしい仕事をされていると思います。
自分や自分の子がHSP傾向が強いと思ったら読む価値は小さくない、というよりもしかしたら劇的に好転させられるかもとさえ思います。
特に「ひといちばい敏感な子」は、HSCの親御さんに対する著者の愛情と応援をとても感じましたし、会話の仕方など具体例も多くてなるほどと思う面も多かったです。
私自身、繊細さを大きな大きな短所と感じてきたので(特に学校や社会の仕組み上そう捉えざるを得ないところが多かったので)、客観的に「ただの性格的な特徴だったんだ」とフラットに意識し直すことができてよかったです。
特に親や教育の現場にいる人にとって繊細さや感受性が高い子が存在するという認識は大切だと思います。
私は3人兄弟ですが親は私だけ「変わっている」と思っていたそうだし、吃音とか幼稚園や小学校を拒否するとか他にもいろいろ心配をかけてきたので。
もしHSPという概念を知っていれば、私のことを「ちょっと変わった子」とか「普通から外れた子」ではなく、「性格が繊細で感受性が強い」という原因から考えられたかもしれません。
ただ逆に言うと本に書いてあるような意識しすぎた「特別な」接し方をされず、普通の子と同じように(愛情をもって)ビシバシされてほんとによかったです。親や先生に感謝。なぜなら、もし本に書いてある通りにやたら繊細さや感受性の高さを尊重されていたら、今頃完全に社会から逸脱していた気がします。
あ、また否定的な見方に戻ってしまいました。
そう、親御さんが読まれるのであれば、HSPへの客観的な理解だけ取り入れて教育法は鵜呑みにしないのがいいんじゃないでしょうか、ってことを言いたいです。
なんだかこれ以上書くとぐちゃぐちゃになりそうなので、このへんで。
最後に、Webデザイナーのブログなので関連付けをしておくと、WebデザイナーはHSP傾向が強い人には向いている職業だと思います。調理師からWebデザイナーに転職してから、社会や会社に馴染めないなあ…心が疲れるなあ…っていうのが少なくなりました。
天職かもしれないっていうのは言い過ぎですが、少なくともなんで厨房の仕事を十何年もやってたのにしっくりこなかったのかは納得できた気がします。HSPの定義うんぬんはつっこみどころが多いですが人間には向き不向きがある。これだけは言えるし反対する人は少ないでしょう。
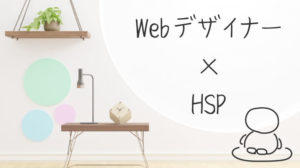
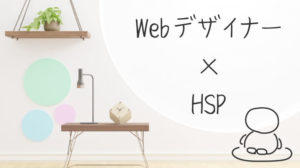
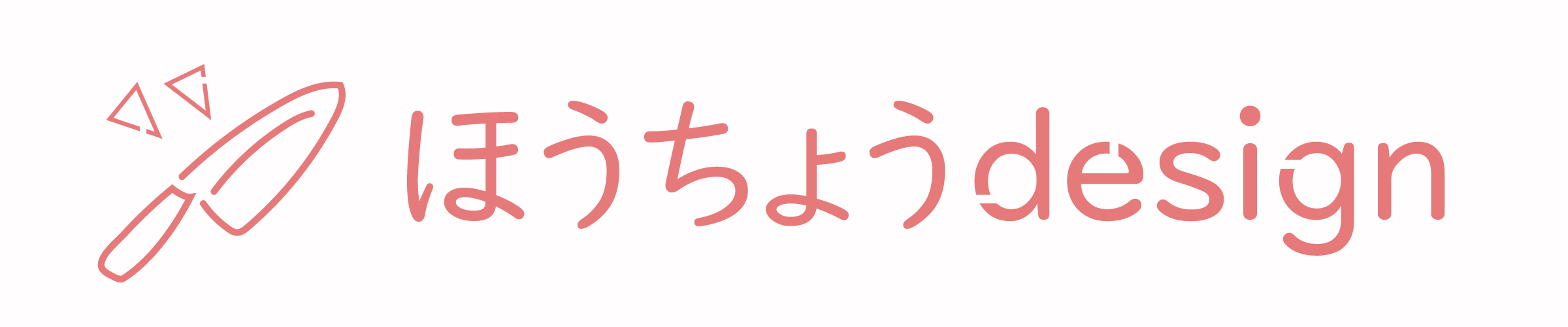
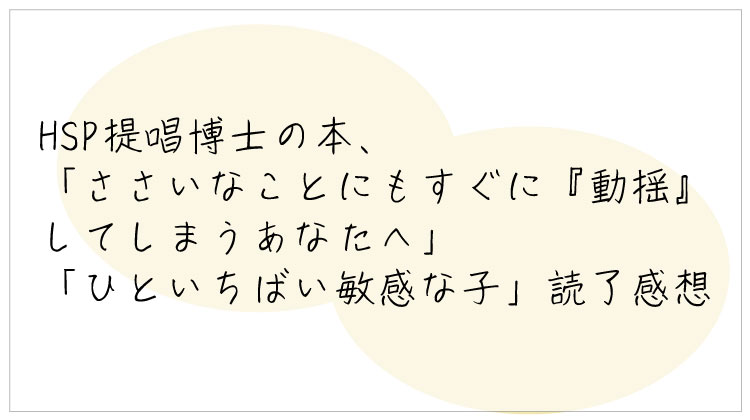


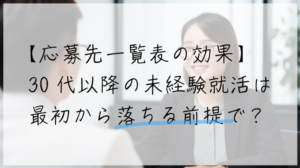
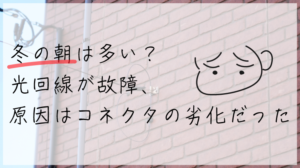
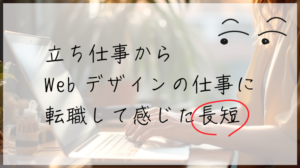
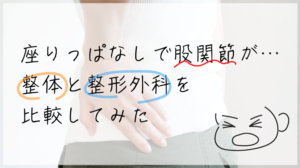
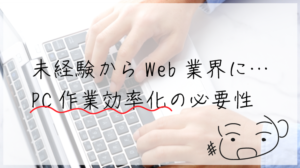
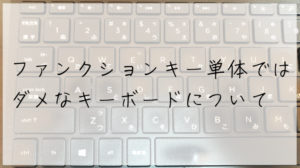
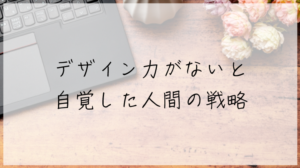
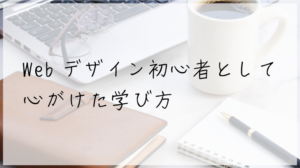
コメント